干し柿を作ってみた! 準備編
- m-maki4
- 2023年11月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年11月15日
こんにちは~清水です。
秋のガス展も終わり11月も半ばに
差し掛かって来ました。
あっという間に今年も後、
1か月半で終わってしまいますね。
毎年毎年1年が、はやく感じるのは、
歳を重ねてきたせいでしょうか。
いいえ!
毎日が充実しているからだと
信じたい今日この頃です。
さて秋の果物と言えば、柿(カキ)。
柿は、ビタミンCが、豊富で風邪や
貧血の予防などの効果がある果物です。
古くから日本で栽培されてきた果物で、
「kaki」世界共通語として名前が、アジアや
ヨーロッパで通用している果実だそうです。
※JAグループHPより引用

部長が、毎年お客様から頂いた柿を「干し柿」にして
作ってくれてお裾分けを頂いておりました。
私は、これまで好んで干し柿を食べた事が
なかったのですが、初めて部長作の「干し柿」を
頂いたとき「甘くてなんて美味しいのだろう!」と
ほっぺたが、落ちた記憶を思い出します。
そんなこんなで…
部長「今年は、干し柿作りに挑戦してみないかい?」
自分「ええ~部長みたいにうまくつくれるかな?」
部長「調べて、清水流で美味しいの期待してるよ!」
自分「はい。それでは、作らせて頂きます。ブログで報告いたします。」
それでは、
レッツ!☆ガッキーチャレンジ!!
「干し柿」の作り方を調べてやってみました。
「干し柿」とは、渋柿を外に吊るして乾燥させたものです。
一般的には、11月~12月に干すのが、よいそうです。
注意する点は、気温と湿度。
雨が続いたり、気温が高いとカビの原因になるそうです。
気温が、10℃以下の日が良いそうです。
渋柿は、渋みが抜けると甘柿よりも糖度が高く、
美味し柿ができるそうです。
(甘がきを干し柿にする人もいますが、
なぜか糖度は渋柿の方が高くなるそうです。)
用意するもの
・渋柿・ビニールヒモ・キッチンバサミ・大きめの鍋
・果物ナイフ(包丁)・ピーラー・
40度以上の焼酎やラム酒など(カビ対策にスプレー)
※ののママキッチンより引用

準備完了!
まず、渋柿の皮を剥いていきます。
はじめは、ピーラーで、キレイに皮を剥いていたのですが、
なかなかスピードが上がらないので、
包丁に持ち替えてムキムキスピードアップ!
何事も不器用で遅いのが、私、清水の特徴ですが、
子供の頃リンゴで鍛えた皮むきの包丁さばきだけは、
はやく上手にできます。

次に剥き終わりましたらT字に残した枝に
紐をグルグル2周くらい廻して結びます。

《※柿を収穫する時、後で紐を吊るせるように
事前に枝をT字で残しておいて下さいね。》

そして紐が、絡まないように注意しながら
鍋にドボンと煮沸します。
熱湯に5~10(秒:煮沸消毒です。)
つけてあげます。
(カビが生えにくくなります。)
今回は、ガスコンロで、御飯が炊ける炊飯鍋を利用しました。
温度低下を最小に抑えられる「火力」が魅力的!
沸騰したお湯が煮こぼれないような大きめのお鍋をご用意下さいね。

最後に、干します。(雨が当たらない場所にしましょう。)
5,6個ずつ干してみましたが、
なかなか均等に上手に干すことができませんでした。
少したってからスプレーボトルに入れた焼酎を
シュッシュ!とまんべんなく吹きかけて終了。
(カビの発生を抑えます)
これで何もせず一週間干したままにします。
一週間経ったら親指と人指し指でやさしく
もんであげると良いそうです。
(早く渋が抜けて甘くなるんだそうです。)
あとは、三日おきにもみ2~3週間経ったら
食べ頃になるようなのでその時が、楽しみです。
表面の白い部分は、糖度の結晶だそうです~
どのくらい白く甘~くなるかワクワクします。
また、ブログにて完成&実食報告したいと思います。
一度自家製の干し柿を食べると、
市販の「干し柿」に戻れないそうです。
私も部長が作って下さった「干し柿」を食べて
体験したことが、これに当てはまります。
自分で作った「干し柿」もその時と
同じ感動を味わえたらいいな~
毎年、実りの秋に柿をお裾分けを
頂いているT様、いつもありがとうございます。

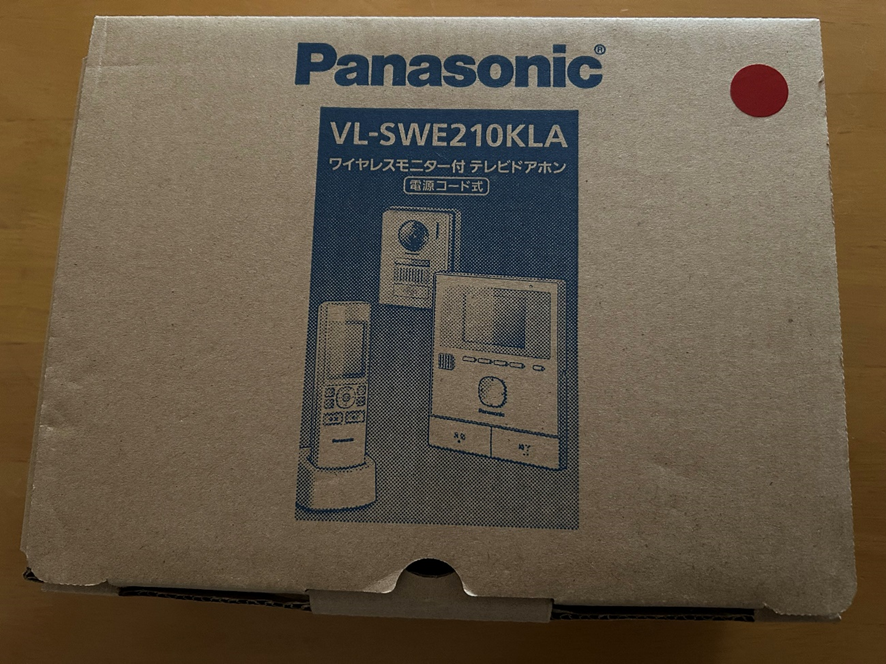


コメント